はじめに
以前の記事で、回帰モデルや分類モデルの評価指標として、MSE(平均平方法誤差)・MAE(平均絶対誤差)やAccuracy(正解率)、ROC-AUCなどの指標をご紹介しました。
しかし、これらの数値だけで「この予測モデルは良い」と判断してしまうのは、医療の現場においてはオススメできません。
ジャーナルで報告されたモデルや、企業が提案してくるAIシステムを使うかどうかを考えるとき、数字には表れない大切な観点を無視してはいけません。
この記事では、「予測モデルの良し悪しを判断するために本当に確認すべきこと」について、医療従事者の目線から解説していきます。
評価指標の数値以外に注目すべきポイントは、例えば次のようなものです。
- 有用性(人間の判断より役立つか)
- 実用性(現場で使いやすいか)
- モデルの妥当性(データや医学的知識と矛盾しないか)
- 誤判定のリスク(外れるときの危険性は許容できるか)
- 責任ある活用(使う側が正しく理解し、判断できるか)
この記事では、これらのキーワードに沿って解説していきます。
評価指標にも興味がある方はこちらの記事で紹介しています。
そもそも予測モデルとは何か?
昨今「予測モデル」と言われるのは、特定のデータから別な事柄を予測するモデルのことです。
特定のデータに当たる物としては、発症時のMRIや胸部CTなどの画像データ・入院時の採血や運動機能のデータなどが挙げられます。
予測モデルの役割は、これらのデータから退院時の運動機能や疾患の有無を判定することです。
なお、「予測モデル」とひとことで言っても、医療現場での使われ方には2種類あります。
この違いを理解しておくと、評価すべきポイントも明確になります。
● 現在の状態を「判定」するモデル
例:CT画像から肺がんの有無を判定する
→ 診断支援モデル/判定モデル
● 未来の状態を「予測」するモデル
例:検査データから10年後に透析になるかどうかを予測する
→ 予後予測モデル
このように、予測モデルには時間軸による違いがあります。
「予測」という言葉のイメージだけに引きずられず、**そのモデルが何を対象にしているのか?**をはっきりさせてから評価する必要があります。
有用性(人間の判断より役立つか)
有用性を判断する3つの視点
モデルの導入価値を判断する最も基本的な問いはこれです。
そのモデルは、医療者が普通に判断するよりも優れているか?
この問いは、次の3つの観点に分けて考えると整理しやすくなります。
🔹 コストの面
- 精度は高くても、非常に高価な検査を必要とする
高価なバイオマーカーやMRIなどが前提なら、導入は非現実的かもしれません。 - 逆に機械的に容易に判定できるものであれば、それをモデルに任せて人間は他の事に時間を使うことが出来ます。結果的に、スタッフのマンパワーを効果的に配分する事につながります。
🔹 時間の面
- 計算に時間がかかりすぎて、予測結果の出力に5時間かかる。
急性期では数時間たつと患者の様態が変わってしまう事もあるでしょう。 - 多数の要因を検討する必要があるケースでは、予測モデルが判定したほうがスピーディーなケースもあるかもしれません。
🔹 精度の面
- モデルのMAEが1.2でも、臨床家の勘による推定の方が誤差が小さい(MAE = 0.7)なら意味がない
人間の判断よりも悪い予測精度では導入価値は薄いことになります。 - 人間には認識出来ないような情報も利用して高精度に判定ができるのであれば、それは非常に有用なモデルと言えるでしょう。
本当に知りたい範囲で精度が出ているか?
精度指標は、全データを対象に計算されますが、それでは本当に知りたいケースにおける性能はわかりません。
例えば…
- 明らかに正常・明らかに異常な症例が多く含まれていて、見かけの精度が高い
- しかし、実際には「人間が悩むような境界例」での精度が低い
このような場合、臨床的な価値は大きく損なわれます。
判断が難しいケースでこそ精度を発揮できるかが、本当の勝負です。
実用性(現場で使いやすいか)
実用性の観点も無視できません。
どれほど精度の高いモデルでも、以下のような「使いにくさ」があると、現場での活用は難しいでしょう。
- 予測に必要な操作が複雑で、専門トレーニングを受けないと使えない
- 診療支援システムと連携しておらず、毎回20件のデータを手入力する必要がある
特に多忙な臨床現場では、「すぐ使える」「手間が少ない」「自動で連携される」といった運用面での設計が極めて重要です。
モデルは目的に応じた利用形態であることが望ましいです。いつでも多数の変数を使用した高精度なディープラーニングモデルが良いとは限りません。
スクリーニングに使用するのが目的であれば、紙などにプリントして誰でも見ればすぐに使えるシンプルな決定木モデルの方が良い場合もあります。
モデルの妥当性(データや医学的知識と矛盾しないか)
ブラックボックスなモデルは、臨床現場での信頼を得ることが難しくなります。
モデルがどのような理由で判断を下したのか、**説明可能性(Explainability)**は重要な評価項目です。
また、モデルが本当に妥当かどうかを見極めるには、次のような視点も必要です。
- 学習データに偏りがないか?
例:高齢者中心のデータで学習したモデルは、小児への予測に向いていません。 - 自施設の症例傾向と合っているか?
例:ヨーロッパのデータで作られた糖尿病予測モデルは、アジア人にそのまま適用すると精度が落ちる可能性があります。 - 医療知識と矛盾していないか?
明らかに医学的に不自然な特徴に依存していないかを確認しましょう。
こうした点を確認することで、モデルの信頼性と現場適合性をより確かなものにできます。
誤判定のリスク(外れるときの危険性は許容できるか)
モデルの精度だけでなく、外れるときのパターンにも注目する必要があります。
- ほとんどのケースで正解だが、時々致命的に大外しをするモデル
- 誤差はあるが、大外しはせず安全な範囲に収まるモデル
前者は医療現場においては非常に危険です。
逆に、説明用資料として使うなどの目的であれば、後者のようなモデルでも十分役立つ場合があります。
モデルをどう使うのか?
どの程度の誤差まで許容されるのか?
これは利用目的とリスク許容度によって変わる、という視点が大切です。
責任ある活用(使う側が正しく理解し、判断できるか)
AIを活用する際に最も重要なのは、医療従事者が責任を持って使うという姿勢です。これはモデル側の問題ではありませんが、運用上では大事なポイントになります。
「モデルが陽性と判定したから介入する」という理由だけで判断をしてはいけません。
モデルの性能や限界、前提条件をきちんと理解し、自らの判断の補助として使うという立場が求められます。
AIにすべてを委ねるのではなく、**「責任ある活用」**が重要です。
まとめ:評価指標の数値が良い=臨床で役立つ、とは限らない
予測モデルの性能を評価するとき、MAEやAccuracyといった数値は有用ですが、それだけでモデルのすべてを理解することは出来ません。
- 臨床で使いやすいか?
- 判断に迷うケースで強みを発揮するか?
- 外れるときのリスクは許容できるか?
こうした多面的な視点を持つことが、AI・予測モデルを医療に活用するうえで欠かせないアプローチです。



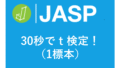
コメント